あなたのお子さんは、順調にピアノが上達していますか?
なかなか上達しない子や、頑張っているのに成果が出ずに悩んでいる、という方はとても多くいらっしゃいます。
今回は、ヤマハ音楽教室で運営管理をしていた筆者が、約1000名の生徒さまの成長を見てきた経験から、ピアノの上達が早い子についての特徴をまとめてみました。
ピアノの上達が早い子どもに共通する3つの特徴

ピアノの上達が早い子には、いくつかの共通点があります。
以下に3つを例としてあげてみました。
- 指先の器用さなど、生まれもっての特性がある
- こまめな練習を習慣化する適性
- リトミック経験があるか
以下にそれぞれ詳しく解説いたします。
指先の器用さなど、生まれもっての特性がある
もともと指先が器用な子、手が大きい子、指が長い子などは、練習においてつまづくことが少ない傾向にあるため、やはり上達のスピードは早くなります。
しかし、上記に当てはまっていないからといって、ピアノに向いていないとは限りません。
今後の練習方法によっては十分に才能を発揮することができます。
こまめな練習を習慣化する適性をもっている
ピアノは1日頑張っただけでは上達しません。
出来るだけ毎日、回数を分けてこまめに練習しているお子さんの方が、確実に上達が早いです。
例えば「1日1時間の練習」を目標にするとしましょう。
- 学校から帰宅して宿題を終えてから、夕方の疲れた時間にみっちり1時間練習するパターン
- 学校へ行く前に15分だけ練習、帰宅後すぐに30分練習、夕食の前に15分練習するパターン
さて、どちらの方が上達が早いでしょうか?
答えは②です。
集中力が途切れないようにこまめに練習を重ねる子のほうが、上達スピードが早い傾向にあります。
リトミック経験があるか
リトミックの経験によって、大きくなった時にピアノの上達速度が変わってくることは、実はよくあることなのです。
聴いたメロディーの音階が分かる「絶対音感」を身につけるためも、5歳までの音楽教育が大切と言われています。
その他にも、幼い頃から音楽に触れることによって、音感やリズム感、表現力、創造性など、将来ピアノを演奏するにあたって大切な感性が育てられます。
リトミックとは?
0〜4歳程度のお子さんに向けた音楽教育法のひとつです。
様々なジャンルのお歌を聴いたり歌ったり、簡単な打楽器を使ってリズム遊びをしたりします。
ピアノの上達が早い子どもの性格や傾向

ピアノの上達が早い子には、性格の面でも共通点が多くあります。
習い始めた当初はなかなか上達しない子でも、その性格のおかげでじっくり上達していくタイプのお子さんも少なくありません。
筆者が出会ってきた、ピアノが上達する生徒さんの性格の特徴を、2つあげてみました。
失敗しても諦めない粘り強さがある子
負けず嫌いなお子さんも上達は早いです。
他人と比較することも時には役に立ちますが、大切なのは過去の自分との比較です。
「昨日の練習ではできたのに今日はできなかった!悔しい!」
という気持ちが大きければ大きいほど、その日の練習には熱が入るでしょう。
大切なのは、失敗しても癇癪を起こさず、冷静に再挑戦できる粘り強さです。
どうすればうまく弾けるのか、自分なりに考える力も育ちやすい傾向にありますね。
おとなしくインドア指向な子
ピアノは基本的に一人で演奏するものです。
大勢のお友達と外で遊ぶよりも、家の中で一人で遊ぶことを好むお子さんの方が、上達が早い傾向にあります。
外遊びで疲れきってしまうタイプのお子さんに比べると、集中力や体力をピアノのために温存できるため、インドア指向なお子さんのほうが、家庭での練習時間が自然と長く取れるようになります。
ピアノの上達が早い子とそうでない子の決定的な違い
さて、ピアノの上達を早めるために必要なこととは一体なんでしょうか。
それは
「なんのためにピアノを練習するのか」
という根本的なところで、お子さんの描く目標を理解することだと筆者は考えます。
以下に、よく感じていた2つのギャップについて紹介します。
お子さんとご両親の目標の違いがある
よくあるケースとして、お子さんは「ただ楽しく好きな曲を弾きたい」という意見であるのに対し、お母さんは「コンクールで賞を取って、将来は音大へ行ってほしい!」と考えているパターンです。
これではレッスンの方向性にも意思の相違が生じてしまい、お子さんはやる気を失ってしまうかもしれません。
先生やピアノ教室を選ぶ際にも、相性はとっても大切なのです。
練習の質と向き合い方の違い
ピアノの上達が早い子は、しっかりと練習の目的を理解していることが多いです。
例えば「このフレーズを1日10回弾くように」と宿題が出されたとしましょう。
上達の遅い子は、ただなんとなく回数をこなすだけなのに対して、
上達の早い子は「このフレーズの指づかいが難しいから、正しく滑らかに、かっこよく弾けるように気をつけよう」と意識して弾きます。
同じ「1日10回」でも、質が全く違いますね。
子どものピアノの才能を見極める方法

まず才能を開花させる前提として「音楽が好きか」という点があげられます。
いつか困難にぶつかったとき、諦めずピアノを続けるために必要な武器として「音楽が好き」であることはとても重要なポイントとなってきます。
さて、生まれつき音楽が好きなお子さんはどんな特徴があるのでしょうか?
音感やリズム感など先天的な素質の兆候がみられる
音楽に合わせて体が動いてしまったり、一度聴いた曲をすぐに覚えてしまうなどの特徴があれば、きっとお子さんは音楽に向いているでしょう。
絶対音感を育てれば、聴いた曲をすぐに弾いて聴かせてくれるかもしれません。
練習への取り組み姿勢
先生に言われた練習内容はもちろん、更に高みを目指して自主的に練習をしてくれるお子さんもいらっしゃいます。
そんな子は「練習」という意識ではなく、遊びの延長で楽しむことが目的となっていますので、きっと上達も早くなるでしょう。
ピアノの上達を早める効果的な練習方法
どれだけ長時間の練習を重ねても、実際に上達がみられなければ意味がありません。
なるべくストレスをかけずに効率的な方法で練習できるよう、時間の使い方を見直してみませんか?
今日からすぐ実践できる、上達につながる練習方法を2つご紹介します。
量より質を重視した練習方法
練習において大切なのは、量より質であるということです。
良質な練習のためには、集中力を途切れさせないための分割練習も大切になってきます。
30分に1回程度の休憩を挟んだり、合間にリフレッシュする時間を設けるのも良い方法ですね。
楽譜を弾く以外のことに着目する
楽譜を読んで鍵盤を弾くことだけがピアノの練習ではありません。
例えば、その曲が作られた時代背景や作曲者の人物像を学ぶことで、曲への理解度が深まり、より味わい深い演奏に仕上げられたりもします。
また、今練習している曲の音源を何度も聴くことも大切です。
目標となる正しい演奏を知らないのと知っているのとでは、上達のスピードも変わってきますよね。
上記のように飽きずに続けられる工夫が重要です。
親ができるピアノ上達のサポート方法
まだ小さなお子さんであれば尚のこと、ご両親のサポートが必須になります。
お子さんが楽しみながらピアノを練習できる環境にしてあげましょう。
家庭での練習環境の整え方
家庭で練習する際の楽器は、上達において重要な役割を担います。
教室で先生に練習曲を披露するときや、発表会など人前で演奏するとき、使用するのはグランドピアノであることがほとんどでしょう。
家庭での練習楽器は、何を使用していますか?
アップライトピアノであれば同じアコースティックピアノなので、弾き心地は悪くないですが、やはりグランドピアノには劣ってしまいます。
電子ピアノやキーボードとなると、弾き心地はほとんど別物になってしまうのです。
そのため、家の楽器では上手に弾けても、
いざ本番になると普段と違う鍵盤なので上手に弾けない
といったケースが多く見受けられます。
やはり、ピアノの上達が早い子は、本番と同じ環境で練習する時間を多くとっています。
楽器店によっては、グランドピアノの置いてある教室を時間単位でレンタルしてくれるところもありますので、利用してみるのも良いですね。
モチベーションを維持するための接し方
お子さん本人にモチベーションを保ち続けてもらうのが、上達の一番の近道ではありますが、それがなかなか難しいものです。
そこで、以前筆者が働いていた教室で行っていた方法を2つあげてみます。
発表会でかわいい衣装を用意する
「上手に弾けるようになったら、プリンセスのドレスを着て発表会に出よう!」と誘う作戦です。
最初はキラキラのドレスを着ることを目標に練習に励んでくれるのですが、案外、発表会そのものを楽しむキッカケになってくれたりもします。
一度人前で弾く経験をすれば、意外と楽しい!ということに気付いてくれる子もとても多いのです。
SNSやYoutubeの活用
最近はネット上でも演奏動画がたくさん出てきます。
そこで憧れの曲や演奏者が見つかれば、話は早いです。
一度、興味のある曲の演奏動画を探してみてはいかがでしょうか?
ピアノの上達が早い子どもの成長目安とタイムライン
よく尋ねられるのが、
「一年でどれくらい弾けるようになりますか?」という質問です。
これは、年齢や練習時間によって大きく異なるので、一概に例をあげることはできません。
しかし、難しいことに挑戦する頻度が多いほど、上達のスピードが上がるのは事実です。
習い始めから一年で見られる成長
年齢にもよりますが「思った通りに弾けずもどかしい」という気持ちが生まれることもあるでしょう。
両手で弾く難しさや、決められた通りの指づかいが嫌で、レッスンが楽しくなくなり「やめたい」と言うお子さんも多くいらっしゃいます。
しかしこれは、難しいことに挑戦しているからこそぶつかる壁なのです。
この壁を乗り越えるために、この記事であげたサポートを屈指して、お子さんを支えてあげましょう。
この努力はきっといつか身を結びます。
長期的な成長における転機
お子さんが成長するにつれて、つまづくことは更に増えていくでしょう。
大きな壁としてあげられるのが、グレード試験やコンクールの課題曲など、普段より難しいことに挑戦する場面です。
この壁を乗り越えられた生徒さんは、演奏面以外の精神面でも、見違えるほどの成長を見せてくれます。
子供の頃から困難の壁に向かうことで得た忍耐力や継続力は、きっと大人になってからも役に立つ場面がたくさん出てくることでしょう。
ピアノの上達が早い子の特徴 まとめ
今回は、ピアノの上達が早い子について、詳しくまとめてみました。
もちろん生まれ持っての才能に影響される部分も少なくはないですが、周囲のサポートや環境を整えることによって、著しい成長を見せてくれるお子さんも多くいらっしゃいます。
この記事が、ピアノを楽しみながら上達できるような手助けになれば、幸いです!

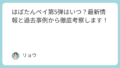

コメント